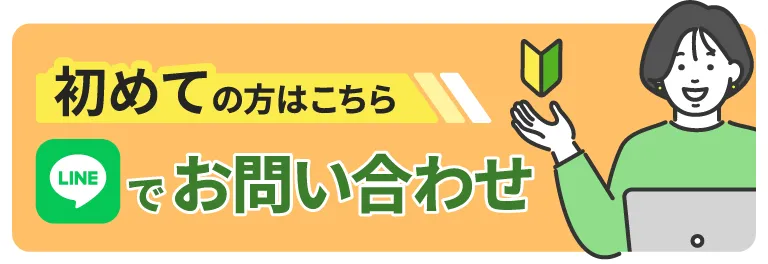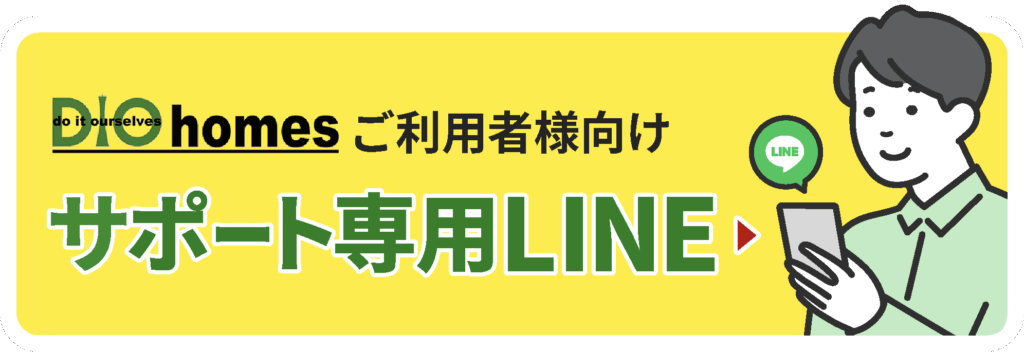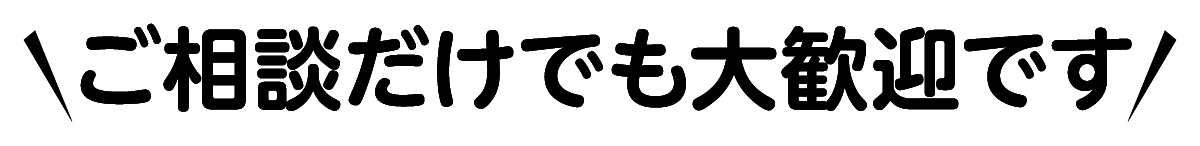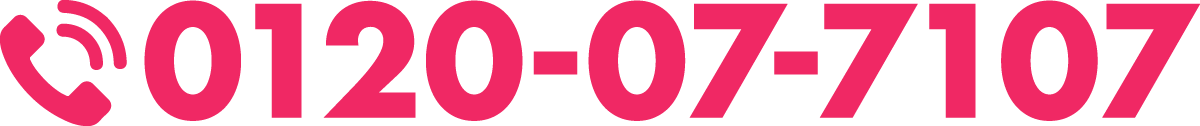遮熱塗料の性能を支える“下塗り”について
遮熱塗料は、太陽光(特に近赤外線)を反射することで建物内部の温度上昇を抑える高機能塗料ですが、その効果を発揮するには、表面状態に合わせた適切な「下塗り材」の選定が不可欠です。実はこの下塗り材の選び方次第で、塗膜の密着性・耐久性・遮熱性能の持続性が大きく変わってくるのです。
なぜ「下塗り材」が重要なのか?
遮熱塗料は上塗りだけでは効果を発揮しません。
むしろ、上塗りの性能を最大限に引き出すためには「下塗り」が非常に重要な役割を担っています。
下塗り材には、主に以下のような目的があります。
- 密着性の確保:塗膜の剥がれや浮きを防ぐ
- 下地の吸い込み止め:仕上がりムラを防止
- ひび割れや凹凸の調整:上塗りの遮熱性能を均一に発揮
- 防錆・防水効果:屋根材の劣化を抑制
- 断熱・遮熱補助効果:近年は機能性下塗り材も登場
このように、下塗り材は見えない部分ですが、仕上がりの美しさと機能性を左右する“縁の下の力持ち”。
遮熱性能を最大化するためには、「塗料の種類だけでなく、下塗り材の選定」にも注意を払うことが欠かせません。
遮熱塗装で使用される下塗り材の種類と役割
遮熱塗料の下塗りには、使用する部位(屋根・外壁)や下地の素材(スレート、金属、モルタルなど)によって、使われる下塗り材が異なります。
ここでは、それぞれの下塗り材が持つ役割と、どんな現場で選ばれているのかを整理します。
| 下塗り材の種類 | 主な用途 | 役割 | 対応下地例 |
|---|---|---|---|
| エポキシ系プライマー | 金属屋根、鉄部、倉庫など | 密着+防錆機能 | ガルバリウム鋼板、トタンなど |
| アクリル系シーラー | モルタル、コンクリートなど | 吸い込み防止+密着 | ALC、サイディングなど |
| フィラータイプ | 外壁の下地調整 | クラック埋め+平滑化 | モルタル外壁など |
| プライマー(汎用) | 各種下地の密着性向上 | 上塗り材との密着確保+下地安定化 | 金属・木材・窯業系など |
| 遮熱機能付き下塗り材 | 屋根全体、高遮熱性能を求める場合 | 遮熱効果を上塗りとWで発揮 | スレート、鋼板屋根など |
エポキシ系下塗り材
金属下地に強く、防錆・密着に優れたタイプ。
主に屋根や外壁の金属部(ガルバリウム鋼板、トタン、アルミ)に使用されることが多く、
工場や倉庫などの遮熱塗装でも高頻度で採用されます。
- 錆の進行を抑え、塗膜の長寿命化に貢献
- 上塗り遮熱塗料との相性も良好
- 塗装対象が金属系であれば、ほぼ第一候補
ただし、吸水性のある素材には適さないため、下地確認が必須です。
アクリル系シーラー
コンクリートやモルタルに使われる、浸透性の高い下塗り材。
素材の吸い込みを防ぎ、塗膜の密着性を向上させます。
- 遮熱塗料が均一に乗るよう、下地を整える
- 劣化した下地の強化にも効果的
- 一般住宅の外壁塗装にも多用される
注意点として、表面に粉化(チョーキング)が強い場合には、シーラーでは効果不足になるケースもあるため、現場調査での判断が必要です。
フィラータイプの下塗り材
クラック(ひび割れ)補修や、下地の凸凹を平滑化したい場合に使用。
下地の不陸(ふりく)調整を行うことで、上塗りの遮熱塗料が均一な性能を発揮するベースをつくります。
- 0.3mm以下の微細なひび割れをカバー
- モルタル外壁や古いサイディングに適応
- 吹付やローラーによって厚みを調整可能
フィラーはあくまで調整材であり、密着力や遮熱機能は持たないため、シーラーと併用されるケースも多いです。
プライマー(全般)
「下塗り材」の中でも、最も基本となる密着性強化のための材料。
素材と上塗り塗料の接着性を高め、塗装の耐久性を底上げする役割を担います。
プライマーは、上塗り材との密着性を確保するだけでなく、
素地の種類(木部・金属・モルタルなど)に応じて調合された専用タイプが用意されているのが特徴です。
- 「エポキシ系プライマー」は金属に強く、防錆性も高い
- 「アクリル系プライマー」はモルタルやコンクリートに適応
- 素地の吸い込みを抑え、上塗りムラや劣化を防ぐ
また、遮熱塗料との組み合わせにおいても、専用プライマーを使うことで反射効果が均一に広がるため、
性能を最大限に発揮するための「基盤づくり」として欠かせない存在です。
ただし、塗布面の状態や気温・湿度によって乾燥時間が異なるため、
施工の際にはメーカー指定の塗布量・乾燥時間を厳守することが求められます。
おすすめ下塗り材の選び方
- モルタル外壁 → 微弾性フィラー+遮熱シリコン
- スレート屋根 → 水性シーラー(吸い込み止め重視)+遮熱フッ素
- 金属屋根 → 錆止め入りエポキシプライマー+遮熱ウレタン
- サイディング → シーラー or プライマー(材質に応じて)+遮熱セラミック
※劣化状態・素地の種類・施工環境により選定は異なります。
遮熱機能付きの下塗り材も存在!?
近年では、反射率の高い「遮熱機能付き下塗り材」も登場しています。
上塗りの遮熱塗料だけでなく、下塗りの段階から熱を反射することで、ダブルで効果を発揮する設計になっています。
- 屋根面の高温対策として注目される
- 特に夏場の日射量が多い地域で有効
- 価格はやや高めだが、効果と耐久性の面で支持される
ただし、全ての施工現場で必要というわけではなく、現場環境と予算を見ながら選定することが重要です。
下塗り材の選定ミスが与える影響とは?
下塗りが不十分な場合、どれほど高性能な遮熱塗料を使っても早期剥離やムラが生じ、十分な効果が得られません。遮熱塗料の高反射顔料は、膜厚・塗布量が設計値から外れると、想定された効果が大きく損なわれます。これを防ぐためにも、下塗りは単なる下地処理ではなく、遮熱塗装の“土台”なのです。遮熱塗料の効果を発揮できない原因として、「下塗り材の選定ミス」が挙げられることが少なくありません。
よくあるトラブルには、以下のようなものがあります:
- 塗膜の剥離、膨れ、浮き
- 遮熱効果の低下(塗料が定着せず、本来の性能が出ない)
- 数年で再塗装が必要になるなど、耐久性の低下
とくに、屋根材の種類や下地の劣化状態に適さない下塗り材を使ってしまうと、遮熱以前に「塗装自体が失敗する」リスクが高まります。
また、工程を省略して下塗りを省いてしまったり、乾燥時間を守らずに上塗りを行うと、
施工不良によって遮熱機能がほとんど発揮されないという事態にもなりかねません。
だからこそ、遮熱塗装を成功させるには、「塗料の選定」と同じくらい「下塗り材の選定」も重要なのです。
プロの視点から見る「下塗りで差がつく現場」
- 例①:劣化の激しいスレート屋根にシーラーを2回塗りして密着強化→剥がれなしで遮熱効果が長期間持続
- 例②:金属屋根に不適切なプライマー使用で半年後に剥離→再塗装が必要に
- 例③:築30年の外壁にフィラー処理を省略した結果、凹凸にムラが出て遮熱効果に差が出た
まとめ|遮熱塗装の「品質」は下塗りで決まる
遮熱塗装を長持ちさせ、十分な効果を得るには、下地の素材や劣化状態に合わせて適切な下塗り材を選定することが最も重要です。
誤った選定や雑な施工は、遮熱性能の低下だけでなく、早期劣化や剥がれといった深刻な問題につながります。
また、下塗り材の選定によって、最終的な施工コストにも影響があります。
一度しっかりとした下地処理をしておけば、再塗装のサイクルを伸ばすことができ、トータルコストを下げることも可能です。
遮熱塗装を業者に依頼する際は、「どの下塗り材を使うか」「なぜそれを選ぶのか」までしっかり確認することをおすすめします。
専門業者であれば、必ず下塗り材に関する説明があり、適切な判断のもとに施工が行われます。
目には見えない部分だからこそ、「下塗り材」は塗装全体の品質を左右する重要なポイント。
遮熱塗料の効果を最大限に引き出すためにも、ぜひ“下塗りの選定”にも注目してみてください。