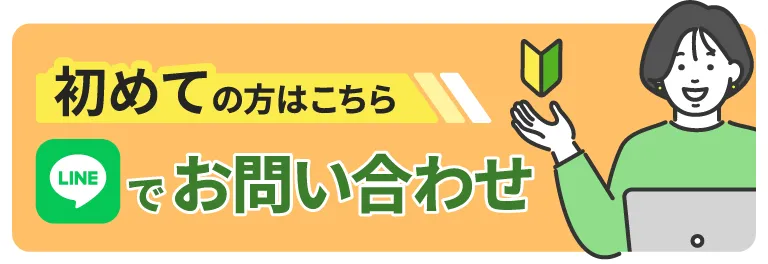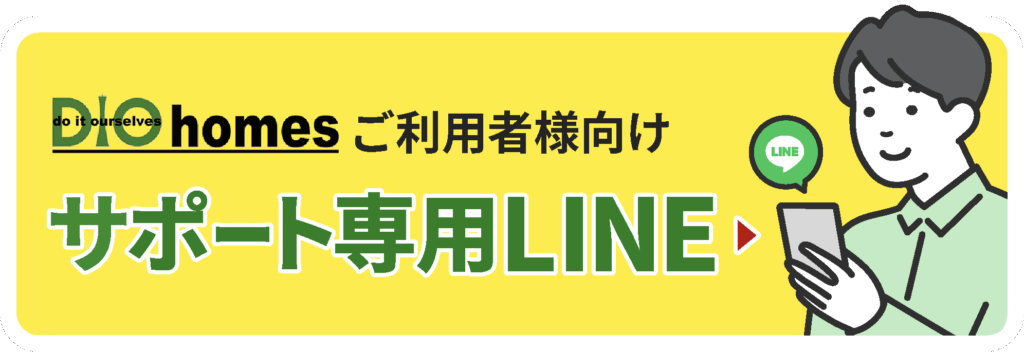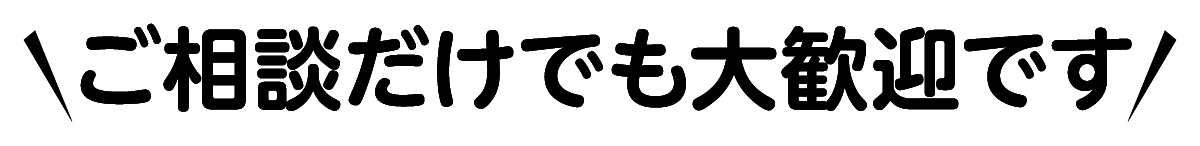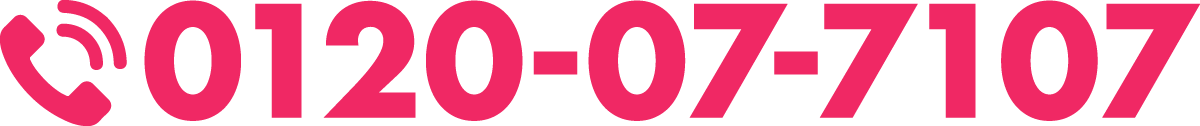実は注意が必要!遮熱塗装が効きすぎて困るケースとは?

遮熱塗装は、夏の暑さ対策・電気代削減・快適な住環境の実現に効果があるとして、
多くの方に選ばれている人気の施工です🤗
しかし一方で、「遮熱塗装が効きすぎて、逆に困った…」
という声が出るケースもあることをご存知でしょうか❓
どんな優れた技術でも“使いどころ”や“環境”によっては
想定外の影響を及ぼすことがあります😥
この記事では、遮熱塗装に関する
“効きすぎ”によって生じる3つのケースとその対策を、
現場の経験に基づいてわかりやすく解説します💁♀️
遮熱塗装が「効きすぎる」とはどういうこと?
遮熱塗装は、太陽光の中の赤外線(熱エネルギー)を反射することで、
屋根や外壁が熱を吸収しにくくする仕組みです👍
しかしこの機能がうまく働きすぎると、
以下のような“想定外”の事態が起こることもあります😯
ケース1:冬場に室内が暖まりにくくなる
「遮熱塗装をしてから、冬の室内が寒くなったような気がする…」
こうしたご相談は多くはないものの、
実際に一部のお客様から寄せられることがあります🤔
遮熱塗装は、屋根や外壁に太陽光を反射する塗膜を形成し、
建物が熱を吸収しにくくすることで、
夏の暑さを軽減するための工法です🌷
その性能は特に赤外線(熱線)を反射することで発揮され、
屋根や外壁の表面温度を大きく下げることができます🌡️
しかしその一方で、冬の寒い時期にも日差しを反射してしまうため、
「これまでなら日光で自然に暖まっていた場所」が
遮熱塗装後には暖まりにくくなるケースがあるのです⚡
特に南向きや西向きの外壁・屋根は、
冬でも比較的日当たりが良く、
日中の温かさを得やすい場所です😌
そこに高反射の遮熱塗料を使用すると、
「暖まりやすさ」がやや失われる可能性があります😣
ただし、これはあくまで
“建物の構造や立地条件によって起こる可能性がある”という話であり、
すべての住宅に当てはまるわけではありません🍀
また、実際に冬の寒さが深刻になるほどの変化があるかというと、
多くの場合は「体感的に少し寒く感じる」レベルで、
室温が明確に低下するケースは少ないと考えられています。
対策として考えられること:
- 南向き外壁など「日照による自然な暖かさを得やすい面」には遮熱塗料を使用しない
- 遮熱性能がマイルドな塗料(反射率を抑えたタイプ)を選ぶ
- 冬の快適性を補うために、断熱材や内窓(Low-E複層ガラスなど)と組み合わせる
ケース2:屋根裏の温度が下がりすぎて結露が発生
遮熱塗装によって屋根の表面温度が下がると、
屋根裏空間が冷やされることがあります⛄
これは夏場にはありがたい効果ですが、
冬場には思わぬ問題=「結露」を
引き起こすことがあるため注意が必要です❗
結露のメカニズムとは?
冬の時期、室内の暖かい空気は
天井を通って屋根裏に上昇していきます🎈
このとき、遮熱塗料によって
冷たくなっている屋根裏側の構造材や野地板に暖気が触れると、
空気中の水蒸気が冷やされて水滴となり、結露が発生します💧
この結露が繰り返されると、
以下のような住宅トラブルにつながる可能性があります💦
- 木材や断熱材が濡れてカビ・腐朽の原因になる
- 金属部分が錆びて構造にダメージを与える
- 天井裏の湿気がこもり、住まいの耐久性に影響することも
特に、屋根裏の換気が不十分な家、
断熱が弱い家、室内で加湿をよく行う家では、
結露のリスクが高まります😣
DIOhomesが現場で実際に見た例:
ある築20年の木造住宅では、
遮熱塗装後の冬に天井裏から異音がすると相談を受け、
点検したところ、
野地板の裏側にびっしりと水滴がついていたケースがありました😱
原因は、屋根裏の断熱材のズレ+棟換気が設けられていなかったこと。
遮熱塗装の効果が高まることで、
かえって冷え込みが強くなり、
結果的に結露が発生しやすくなってしまったのです。
対策として有効なこと:
- 屋根裏に棟換気・軒天換気などの通気経路をしっかり確保する
- 断熱材の再点検・補強で、冷気と暖気の接触を減らす
- 室内の過度な加湿(加湿器の使いすぎ)を避け、湿度コントロールを意識する
- 遮熱塗装の際に、結露の可能性を事前にチェックする
ケース3:外壁や周辺の環境に思わぬ影響が出る
遮熱塗装は太陽光、特に赤外線を反射して
熱の侵入を抑えるのが目的ですが、
同時に可視光(目に見える光)も反射する性質を持っています。
この“高反射”が、場合によっては
「まぶしさ」「光害(ひかりがい)」といった形で
近隣に悪影響を与えることがあるのです。
よくあるトラブル事例:
- 南向きの屋根に明るい遮熱塗料を塗ったところ、午後になると隣家の窓ガラスに反射して強烈なまぶしさを生んでしまった
- ベランダ床に遮熱トップコートを施工したが、照り返しが強くて洗濯物を干すのがつらい
- 駐車場の車に光が反射して、ダッシュボードやフロントガラスがまぶしくなった
- 家の中にいても、白い壁に反射した光が天井や床にチカチカ映り込むようになった
このような問題は特に、以下の条件で起きやすくなります:
- 使用した塗料が白・アイボリー・シルバーなどの高反射色だった場合
- 艶あり仕上げ(グロス)で、表面がピカピカに仕上がっている場合
- 近隣との距離が近く、建物同士が向き合っている住宅地
遮熱塗装の効果として
「反射性が高い=よく効いている」ということにはなるのですが、
快適性や地域との調和という観点から見ると、
必ずしもプラスとは限らないのが難しいところです。
対策:まぶしさ・照り返しで近隣に迷惑がかかる定で“反射しすぎ”を抑える
光の反射によるトラブルを防ぐためには、以下のような工夫が有効です。
- 3分艶・艶消し(マット)仕上げの遮熱塗料を選ぶ
→ 光の反射が和らぎ、周囲への影響が出にくくなる - 中間色・落ち着いた色味(グレー系・モスグリーンなど)を選ぶ
→ 白に近いほど反射率が高いため、見た目と機能のバランスを取る - 屋根は遮熱、外壁は通常塗料など、面ごとの塗料使い分けを検討
- ベランダやバルコニーは、床面の艶を抑えた仕様で照り返しを防ぐ
また、事前に太陽の入り方・建物の方角・近隣との距離などを
調査することで、リスクを把握した上で塗装プランを立てることが可能です。
遮熱塗装の“効果”はバランスが大事
遮熱塗装はたしかに優れた性能を持っていますが、
家全体の構造や暮らし方とのバランスを取らないと、
逆に快適性を損ねる可能性もあるのです。
DIOhomesでは、「ただ塗る」だけでなく、
お住まいの状況や季節ごとの体感温度まで考慮したプラン提案を大切にしています。
まとめ|遮熱塗装は“良さを活かせる施工”が成功のカギ
遮熱塗装は、適切に使えば夏の室内温度を抑え、
冷房効率を上げ、光熱費を節約できる非常に有効な塗装工法です。
しかし、全ての住まいに“無条件で最適”というわけではなく、
使い方を間違えると、思わぬ不便やトラブルを招くケースもあります。
今回ご紹介したように、遮熱塗装が
「効きすぎて困る」ケースには以下のような例があります:
- 冬場に太陽熱を反射しすぎて、室内が暖まりにくくなる
- 屋根裏が冷えすぎて、結露の原因になる
- 表面が光を強く反射して、近隣にまぶしさの迷惑をかけてしまう
こうした問題は、遮熱塗料そのものが悪いのではなく、
塗る場所・使う色・建物の構造・環境との“相性”に
原因があることがほとんどです。
だからこそ、遮熱塗装を検討する際には
「とにかく遮熱性の高いものを塗ればいい」という考え方ではなく、
- どこに塗るのが最も効果的か
- どの程度の反射率・艶感が合っているか
- 断熱・換気など他の要素とどう組み合わせるか
といった“全体のバランス”を見極めることが成功のカギになります。
DIOhomesでは、お客様の住まいの構造・方角・周囲の建物・断熱状況などを丁寧に調査し、
「本当に遮熱塗装が必要かどうか」から正直にご提案しています。
ときには、遮熱塗料よりも「汚れに強い塗料を優先すべき」
「濃い色を活かした通常塗料の方がデザインに合う」
といったアドバイスをすることもあります。
「効きすぎ」も「効かなすぎ」もない、“ちょうどいい遮熱塗装”をご提案します
遮熱塗装は、ただの省エネ対策ではなく、
住まいの性能を底上げする一手にもなり得る存在です。
しかし、その力を最大限発揮するためには、
目的に応じた判断と、プロによる的確なプランニングが必要です。
「夏を快適にしたいけれど、冬の寒さも不安」
「遮熱塗装に興味があるけど、うちの家に合うかわからない」
そんな方は、ぜひ一度DIOhomesにご相談ください。
経験豊富なスタッフが現地を丁寧に調査し、
“効きすぎない、でもしっかり効く”遮熱塗装プランをご提案いたします。